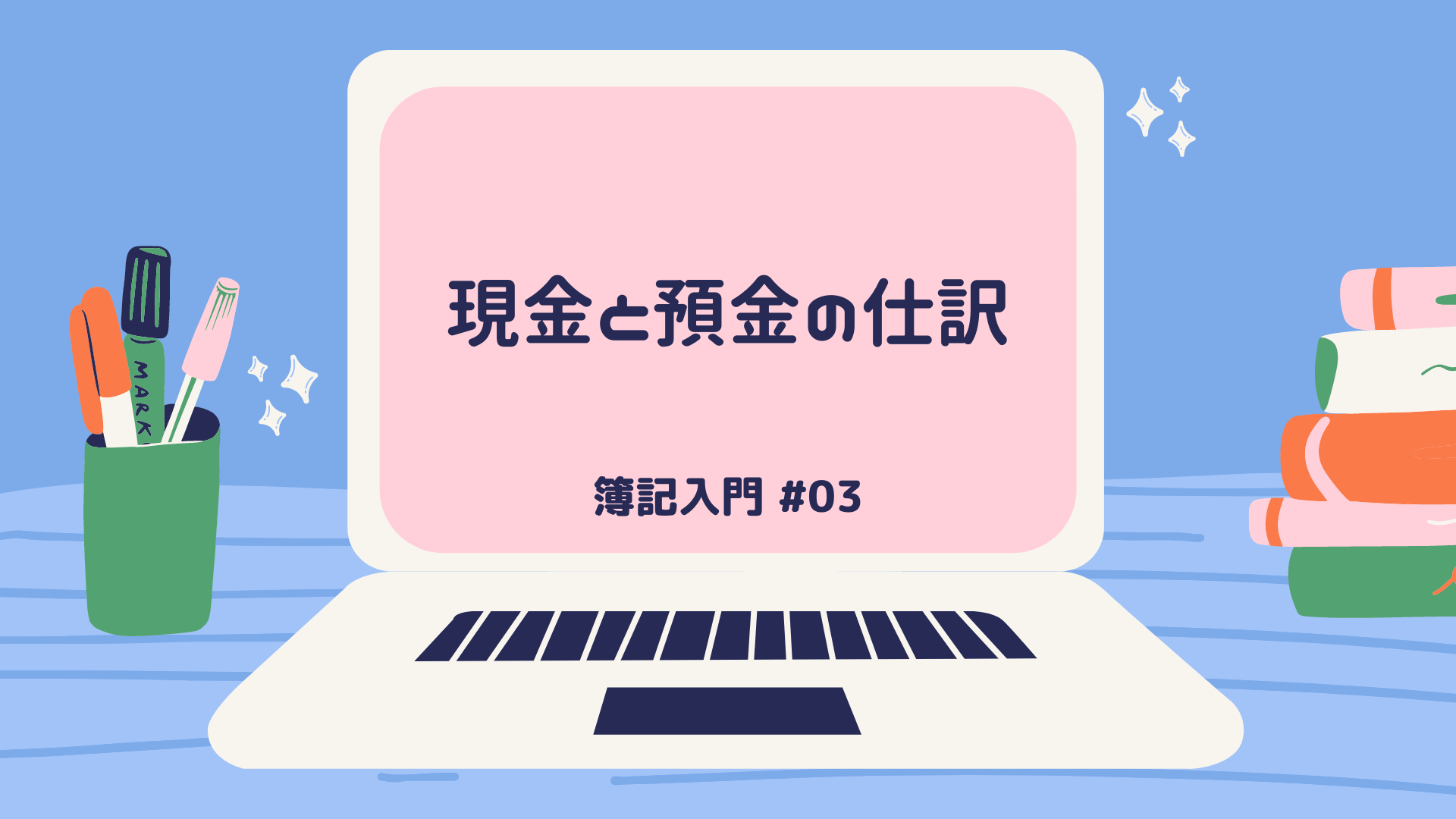現金の仕訳
現金の仕訳をマスターするためには、押さえておくべきポイントが主に3つある。
- 通貨代用証券
- 現金過不足
- 小口現金
以下、それぞれについてみていく。
1. 通貨代用証券
簿記では、実際に手元にある現金だけでなく、すぐに換金できるものも現金扱いする。
具体的には、
- 配当金領収書
- 郵便為替証書
- 他人振り出しの小切手
などが該当し、これらを通貨代用証券と呼ぶ。
2. 現金過不足
日々の仕訳の中では、手元にある現金の残高と、実際の現金残高に不一致が生じることもある。
高した時、暫定的に現金過不足という勘定科目を用いて仕訳を行う。
後ほどその不一致の原因が判明した場合は、その内容に応じて仕訳を行う。
3. 小口現金
実際の経営において、支出の都度に出納と仕訳を行うのは、時間も手間もかかり現実的ではない。
そこで、まとまった現金をあらかじめ用度係に渡しておき、報告に基づいて後程まとめて仕訳を行うことが多い。
この、まとまった現金を小口現金と呼ぶ。
預金仕訳の予備知識
続いて、預金口座の仕訳について整理する前に、必要な予備知識を確認しておく。
当座預金と小切手
銀行口座には、普通預金と当座預金がある。
当座預金には以下のような特徴がある。
- 小切手や手形を扱える
- 開設には銀行の審査を受ける必要がある
- 通帳が発行されない
- 利子がつかない
一般的に、当座預金を開設する主な目的は、小切手を使えるようにすることであると言える。
小切手は、様々な支払いに使うことができる。
このため、当座預金を開設すると手元にあまり現金を持たなくて良くなるというメリットがある。
預金の仕訳
預金口座が関与する仕訳には、以下のようなポイントがある。
- 小切手取引
- 自己振出の小切手
- 当座借越(とうざかりこし)
- 複数の口座を開設している場合
以下、それぞれ具体的にみていく。
1. 小切手取引の仕訳
小切手の仕訳においては、仕訳のタイミングと勘定科目に気をつける必要がある。
小切手を振り出したとき
- 振り出した側:その時点で「当座預金」が減少したものとする。
- 受け取った側:その時点で「現金」が増加したものとする。
← 「他人振り出しの小切手」なので、仕訳上は通貨代用証券 = 現金に相当する。
小切手を換金したとき
双方ともに仕訳なし。
2. 自己振出の小切手
実際の業務ではあまりないが、自分が以前に振り出した小切手が、回り回って自分のところに帰ってくることは、理論上はあり得る。
こうした自己振出の小切手を受け取った場合は、帳簿上は勘定科目を「当座預金」として処理する。
3. 当座借越(とうざかりこし)
企業は通常、日々の円滑な資金調達のため、銀行と「X 円までであればいつでもすぐに借りられる」という当座借越契約を結んでいる。
この「X 円」という限度を、「枠」や「限度額」
そして、お金を借りた結果残高がマイナスになることを当座借越という。
ただし、日常の仕分けでは、一々マイナス分の名称変更を行わず、「当座預金」として処理してしまうことも多い。
この場合は、決算整理仕訳でマイナス分を「当座借越」に名称変更する。
このように、「当座預金」勘定を用いて日常のマイナス分を仕訳する方法を、一定勘定という。
※ マイナス分をその都度「当座借越」で表現する二勘定制もある。
4. 口座を複数開設している場合の仕訳
口座を複数開設している場合は、勘定科目でそれぞれの銀行名を付記し、書き分けるようにする。
たとえば、A 銀行と B 銀行にそれぞれ当座預金を開設している場合は、
- 当座預金 A 銀行
- 当座預金 B 銀行
というふうに表現する。
※ 口座ごとに勘定科目を設定しない書き方もできるが、その場合は別途補助簿を作る必要が生じる。
まとめ
現金・預金の仕訳の基本は上記の通りだが、具体的な仕訳に慣れるには、本や動画、講座などで学びながら、反復練習を行う必要がある。
上記の内容は、以下の書籍を参考とした。

ホントにゼロからの簿記3級 『ふくしままさゆきのホントに』シリーズ