スイス・スタイル Swiss Style(1950年代〜)
スイス・スタイルは、1950年代にスイスで生まれ、オーロッパを中心に流行したグラフィックデザインのスタイルである。国際タイポグラフィ様式とも呼ばれる。
グリッド・システムに基づく合理的かつ秩序立ったフォーマット、プレーンで機能的なサンセリフ体の統一使用など、厳密なルールによる理知的なデザインは、情報をわかりやすく正確に伝えることを重視している。
1957年には、Helvetica、UNIVERSという二つの代表的なサンセリフ書体が、いずれもスイスを中心とするドイツ語圏で作られた。
見出しから本文まで統一的に使用できる豊富なファミリーを備え、無機質で汎用性の高い書体は、現在でも出版や広告などに欠かせない、スタンダードな書体として定着している。

※ グリッド・システム:ページ内に縦横に等分した格子状のガイドライン(グリッド)をもうけ、それを基準に画像や文字を配置するレイアウト手法。グリッドレイアウト。
※ ファミリー:ある統一された設計方針を持つ書体の、ウェイト(文字の太さ)やスタイル(イタリックなど)が異なったバリエーションを含めたセットのこと。
オプ・アート optical art(1950年代〜)
オプ・アートはオプティカル・アートの略で、目の錯覚などの視覚のメカニズムを利用した錯視の芸術を指す。
「動いているように見える」「立体的に見える」「明滅して見える」など、鑑賞者に特殊な視覚効果を与えるような絵画や立体作品を指す。騙し絵(トロンプ・ルイユ)がルーツと言われている。
現代抽象芸術の一ジャンルであり、幾何学的な図形を用いるのが特徴。
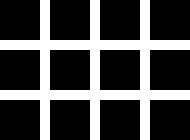
ウェブデザインにおけるパララックス効果にも影響を与えている。
※ トロンプ・ルイユ:フランス語で「目を欺く」の意。トリックアートとも呼ばれ、壁面等に実物とみまごう精巧な描写で窓や人物などを描き、まるでそこに本物があるように見せる作品。マウリッツ・エッシャーに代表されるような、建築不可能な構造物などを描いた作品も含まれる。
※ パララックス効果:「視差効果」の意。ウェブ画面のスクロール操作に応じて複数のレイヤーに分けた要素のスクロール速度を変えることで、「視差」を生み出し、擬似的に立体感や奥行きを感じさせる手法のこと。
スカンジナビアン・モダン scandinavian modern(1950年代〜)
スカンジナビアン・モダンは、北欧のスカンジナビア半島周辺国によるデザインの総称である。
北欧モダンとも呼ばれ、ハンス・ウェグナーのYチェアに代表される家具や、イッタラのガラス製品、アラビアの陶器など、インテリア・日用品が有名。
1951年のミラノトリエンナーレを契機に、1950〜1960年代に世界的ブームとなった。

イッタラ<アルヴァ・アアルト コレクション>
特徴は機能的でミニマルな造形や、温かみのある自然素材や色使い。
伝統的な手工芸も重んじられ、職人の手仕事と合理的な工業生産の結びつきが、居心地の良さとモダンさの両立に結びついている。
ミニマリズム minimalism(1960年代〜)
ミニマリズムは、ミニマル(最小限の)という意味を持つ美術、建築、音楽などの分野で、
形態や色彩を最小限度まで突き詰めようとする最小限主義のことを指す。
1960年ごろから潮流が起こり、現在では建築やプロダクトだけでなく、ウェブデザインなどにも大きな影響を与えている。
有名な言説として、
モダニズム建築を推進する建築家アドルフ・ロースの「装飾は罪悪である」、
ルイス・サリヴァンの「形態は機能に従う」、
ミース・ファン・デル・ローエの「Less is more(より少ないことは、より豊かなこと)」
などがある。

スペースエイジ space age(1960年代〜)
スペースエイジは、アメリカとソ連による宇宙開発競争が盛んだった1960〜1970年代に流行した、近未来的なデザインを指す。
その影響は家具や家電、ファッション、建築、映画、音楽など多岐に渡った。
特色としては、時代の未来志向を反映した流線形や球体など、それまでになかった不思議なフォルムと、プラスチック素材などが挙げられる。

エーロ・アールニオ<ボールチェア>
※ レトロフューチャー:スペースエイジの時代の人々が思い描いた明るい未来のイメージを、「訪れなかった未来像」として懐かしむ思いから、1980年代に流行した潮流。
ブリコラージュ bricolage(1960年代〜)
ブリコラージュは、寄せ集めて自分で作ったり、物を自分で修繕することを指す。「器用仕事」とも呼ばれる。
その場で手に入るものを部品として、新しいものを作り出すことであり、広義には原始時代の土器、ありあわせのものでピンチを乗り越える神話や物語、現代の情報技術などもブリコラージュの一種と言える。
ブリコラージュという言葉が広まったのは、フランスの文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースの著書『野生の思考』(1962年)などで、本来の用途とは関係なく当面の必要性に役立つ道具を作ることを「ブリコラージュ」と読んだことがきっかけだと言われている。
サイケデリック psychedelic(1960年代〜)
サイケデリック(サイケ)とは、LSDなどのドラック服用時の幻覚症状や恍惚・トランス状態、心理的感覚や、それらを想起させる美術や音楽を指す。
1950年代に精神科医のハンフリ・オズモンドが、ギリシャ語のpsychē(精神・魂)とdēlos(目にみえる)(または英語のdeliciou(美味しい))を組み合わせた造語と言われている。
具体的な特徴は、原色や蛍光色の刺激的な色彩模様、閃光が明滅する映像、ドラッグの酩酊状態で演奏された浮遊感のあるロックミュージックなどである。
1960年代のヒッピー文化と結びついてムーブメントとなり、レコードジャケットやファッションなどのデザインを通して東西の若者に流行した。



